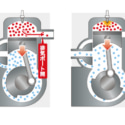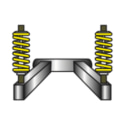バイク用語辞典
『た行』から始まる用語
-
電子制御サスペンション
-
チャンバー
主にバルブを持たない2ストロークのエキゾーストパイプ中央部に設けられた膨張室のこと。排気圧をコントロールすることでバルブの代わりをしたりしてエンジンの特性を変えている。
-
定地走行燃費
-
トリップ(メーター)
走行距離を表示するメーター。リセットできるので任意に走行距離を計測できる。
-
チューニング
エンジン内部の研磨やキャブレターの調子を整え、性能の向上を図ること。または、自分好みの設定にすること。
-
取りまわし
駐輪時や狭いところを移動する際、エンジンを切った状態でバイクを押して歩くこと。それら押し歩き作業全般を“取りまわし”という。バイク雑誌などで“取りまわし性”と称してバイクを評価するポイントの一つにすることがあり、たとえば、軽くて細身の車両であれば「取りまわし性(あるいは単に“取りまわし”)がよい」などと表現する。
-
デッドエア
衣服の内部に抱き込まれ、外部に流出しない空気のこと。自分の体温がデッドエアを暖めることで保温効果が得られる。
-
トルク
クランク軸を中心に1m先に付けたおもりを何㎏まで動かせるかということ。実際には、エンジンの力強さを表す言葉として「厚みのあるトルクが…」とか「トルクフルなエンジン性能」などと表現される。また、ネジを締め付ける力にもトルクという言葉が使われ、ネジの太さや材質によって規定値が異なる。エンジンオーバーホールなどの重整備には締め付けトルクを測定することができるトルクレンチが必要不可欠。
-
トレッド
タイヤの路面と接する部分のこと。刻まれた溝のデザインをトレッドパターンという。
-
鋳造(ちゅうぞう)
一度溶かした金属を型に流し込んで成型すること。コストは低く抑えられるが、強度と重量は鍛造に劣る。
-
電動ファン
ラジエターを流れる冷却水は走行風によって冷やされるが、電動ファンはファンの駆動をモーターによって行なうことで冷却する。バイメタルというある一定の温度で反る金属板をスイッチに使い、温度が上がればファンが回り、下がると止まる。
-
電熱ウエア
電気カーペットのように電気で発熱する素材が仕込まれた防寒ウエア。電力を車載バッテリーからとる直結タイプ、バイク以外の用途にも使えるモバイルバッテリータイプ、どちらも使える共用タイプがある。
-
倒立(フォーク)
-
トップケース
車体後部のキャリアに設置するケースのこと。
-
ツアラー/高速ツアラー
風防効果の高いカウルを装備したり、余裕のあるライディングポジションを持つなど、高速巡航時のライダーに対する負担を軽減する工夫をこらした長距離ツーリング向けモデルのこと。ホンダのGoldWingやカワサキのニンジャH2 SX SE+などが該当。
-
トラクション
駆動力。タイヤが地面を蹴って車体を前に進ませようとする力。速く走るためにはつねに安定したトラクションが必要。
-
ツーリング
Touring。バイクで行なう旅行(Tour)のことで、バイクに乗ったら一度はやりたい。クルマでいうドライブや遠乗りに当たるが、距離や期間などによって、日帰りツーリング、ロングツーリングなどと呼ぶ。
-
トラッカー
路面が土の周回路(トラック)でリヤタイヤをすべらせながら走るダートトラックレーサーのスタイルを模したジャンル。かつてのホンダのFTRやスズキのグラストラッカーなどがこれにあたる。
-
DIY
Do It Yourself=自分でする、という意味。カスタムや修理を自分で行なうときに使う。「マフラーをDIYで取り付けた」など。
-
ドラッグ
drag=引っぱる。ドラッグレースといえば、クルマ・バイクの加速競争のこと。停止状態から402.33m(1/4マイル)先のゴールまで、どちらが先にたどり着くかを2台で競い合う。よく試乗記事で「ドラッグ風の〜」とあるが、これは加速性能(の凄まじさ)や低く構えたポジションに対して用いられる表現。